「ホームページを作ったのに患者が来ない」歯科医院が陥る5つの失敗パターン
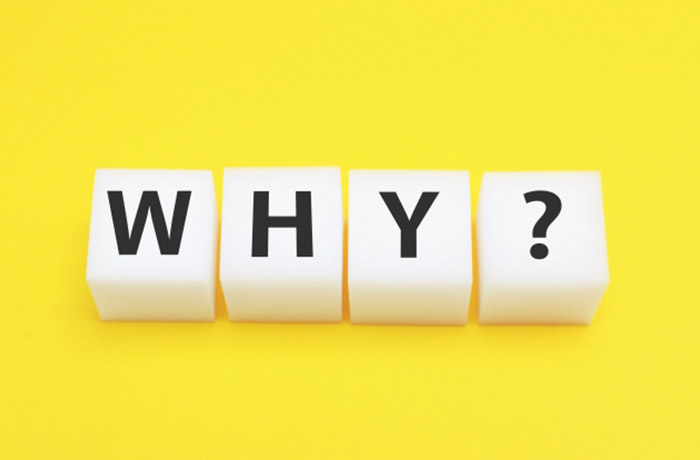
目次
1. なぜ作ったホームページが機能しないのか?
2. 失敗パターン1:検索で見つからない「見えないサイト」
3. 失敗パターン2:医院目線の情報ばかりの「自己満足サイト」
4. 失敗パターン3:信頼感が伝わらない「薄っぺらいサイト」
5. 失敗パターン4:スマホで使えない「時代遅れサイト」
6. 失敗パターン5:更新されない「放置サイト」
7. 失敗から成功への転換方法
なぜ作ったホームページが機能しないのか?
「50万円かけてホームページを作ったのに、全然患者さんが来ない…何がいけないんでしょうか?」
このような相談を、月に10件以上いただきます。せっかく費用をかけてホームページを制作したのに、期待した効果が得られず困惑されている院長先生は決して少なくありません。
実は、歯科医院のホームページで集患効果が得られない理由には、明確なパターンがあります。多くの医院が同じような失敗を繰り返しており、その原因を理解することで改善の道筋が見えてきます。
現代において、患者さんの約半数がホームページを見て歯科医院を選んでいます。つまり、ホームページは24時間働く優秀な営業スタッフのような存在になり得るのです。しかし、間違った作り方をしてしまうと、逆効果になることもあります。
今回は、集患効果の出ないホームページに共通する5つの失敗パターンを詳しく解説し、それぞれの改善方法をお伝えします。もし現在のホームページに当てはまるパターンがあれば、早急な改善をお勧めします。
失敗パターン1:検索で見つからない「見えないサイト」

最も深刻な失敗パターンは、そもそも患者さんに見つけてもらえないサイトです。どんなに素晴らしいデザインや内容であっても、検索結果に表示されなければ意味がありません。
典型的な症状
「地域名+歯科医院」で検索しても、自院のサイトが1ページ目に表示されない。Google検索で3ページ目以降にしか表示されない、または全く見つからない。院名で検索しても上位に表示されない場合もあります。
失敗の原因
多くの場合、SEO対策(検索エンジン最適化)が全く行われていないことが原因です。制作会社が「デザインは綺麗だが検索に弱いサイト」を作ってしまったり、検索エンジンが理解しやすい構造になっていなかったりします。
また、地域に関連したコンテンツが不足していることも大きな要因です。例えば、「○○市の歯科医院」という情報はあっても、地域住民にとって価値のある情報が不足していると、検索エンジンからの評価が低くなります。
改善の方向性
まず、基本的な地域キーワードでの検索順位を確認し、現状を把握することから始めましょう。その上で、地域密着型のコンテンツを充実させ、継続的な情報発信を行うことで検索順位の向上を図ります。
技術的な改善も重要です。サイトの構造を検索エンジンが理解しやすい形に修正し、適切なキーワード設定を行う必要があります。これらは専門的な知識が必要なため、SEOに詳しい制作会社に相談することをお勧めします。
失敗パターン2:医院目線の情報ばかりの「自己満足サイト」

制作したサイトの内容が、医院側の伝えたいことばかりで、患者さんが知りたい情報が不足しているパターンです。このようなサイトは、訪問した患者さんがすぐに他のサイトに移ってしまいます。
典型的な症状
最新の医療機器の説明ばかりが掲載されている。専門的な治療技術の詳細が中心で、患者さんにとってのメリットが分からない。院長の経歴や資格の羅列ばかりで、人柄や診療方針が見えない。
患者さんが本当に知りたい情報
- 治療は痛くないか、時間はどれくらいかかるか • 費用はどの程度かかるか、支払い方法は選べるか
• 初診の流れはどうなっているか、予約は取りやすいか • 院内の雰囲気はどうか、スタッフは親切か • 駐車場はあるか、子連れでも大丈夫か
改善の方向性
患者さんの立場に立って、サイトの内容を見直すことが重要です。技術的な説明よりも、「患者さんにとってどのような良いことがあるか」を中心に情報を整理し直しましょう。
また、患者さんの不安を解消する情報を積極的に掲載することも効果的です。初診の流れを写真付きで説明したり、よくある質問に丁寧に答えたりすることで、来院前の不安を軽減できます。
失敗パターン3:信頼感が伝わらない「薄っぺらいサイト」
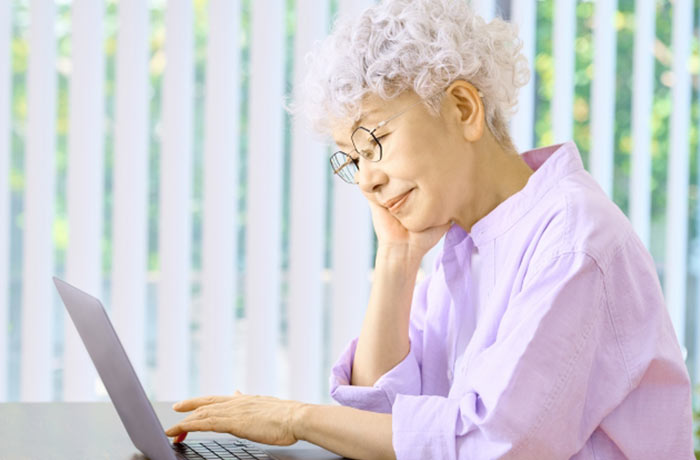
見た目は整っているものの、内容が薄く、医院の人柄や専門性が伝わらないサイトも集患効果が期待できません。患者さんは「この医院に任せて大丈夫だろうか」という不安を解消できずに他院を選んでしまいます。
典型的な症状
どの歯科医院にも当てはまるような一般的な内容ばかり。院長先生の顔写真がない、または小さすぎて人柄が伝わらない。診療方針や治療に対する考え方が曖昧で、特徴が分からない。
信頼感を構築する要素
患者さんが歯科医院を選ぶ最大の決め手は「信頼感」です。技術的な優秀さよりも、「この先生なら安心して任せられる」という感情的な安心感が重要なのです。
効果的なのは、院長先生の診療に対する想いを丁寧に文章で表現することです。なぜ歯科医師になったのか、どのような治療を心がけているのか、患者さんに対してどのような想いを持っているのかを、具体的なエピソードを交えて紹介しましょう。
改善の方向性
院長先生やスタッフの人となりが分かる情報を充実させることから始めましょう。プロフィール写真は大きく掲載し、親しみやすい表情の写真を選ぶことが重要です。
また、院内の雰囲気が分かる写真を多数掲載し、「温かい医院」「清潔な医院」「家族的な医院」など、目指すイメージを視覚的に伝えることも効果的です。
失敗パターン4:スマホで使えない「時代遅れサイト」

現在、歯科医院のホームページへのアクセスの約80%はスマートフォンからです。しかし、スマホ対応が不十分なサイトは、せっかくの集患機会を逃してしまいます。
典型的な症状
スマートフォンで見ると文字が小さすぎて読めない。ボタンが小さくて押しにくい、または反応しない。ページの読み込みが遅く、患者さんが待ちきれずに他のサイトに移ってしまう。
スマートフォンユーザーの行動特性
スマホで検索する患者さんは、「今すぐ歯医者を探したい」という緊急性の高い状態であることが多いです。そのため、必要な情報をすぐに見つけられないサイトは即座に離脱されてしまいます。
特に重要なのは、電話番号がすぐに見つけられ、ワンタップで電話をかけられることです。また、診療時間やアクセス情報も、スクロールせずに確認できる位置に配置する必要があります。
改善の方向性
スマートフォンでの表示を最優先に考えたサイト設計に変更しましょう。文字サイズ、ボタンの大きさ、画像の配置など、すべてをスマホユーザーの使いやすさを基準に調整します。
また、ページの読み込み速度も重要な要素です。画像のサイズを最適化し、不要な機能を削除することで、快適な閲覧環境を提供できます。
失敗パターン5:更新されない「放置サイト」

作成後に全く更新されていないサイトも、集患効果が期待できません。古い情報が掲載されていたり、最新のお知らせがなかったりすると、患者さんは「この医院は大丈夫だろうか」と不安に感じてしまいます。
典型的な症状
診療時間や休診日の情報が古い。スタッフ紹介が以前のままで、現在のスタッフと異なる。お知らせ欄の最新記事が半年以上前のもの。
更新の重要性
定期的な更新は、患者さんに対して「活発に運営されている医院」という印象を与えます。また、検索エンジンも更新頻度の高いサイトを高く評価するため、SEO効果も期待できます。
更新内容は、診療に関する情報だけでなく、季節の健康情報や予防歯科のアドバイスなど、患者さんにとって価値のある情報を提供することが重要です。
改善の方向性
まず、現在掲載されている情報をすべてチェックし、古い情報は即座に修正しましょう。その上で、定期的な更新計画を立て、月1回以上は新しい情報を追加するようにします。
更新作業を負担に感じる場合は、制作会社に更新代行を依頼することも一つの方法です。ただし、その場合も医院側で更新内容をチェックし、正確性を確保することが重要です。
失敗から成功への転換方法
これらの失敗パターンを把握したら、次は具体的な改善行動を起こすことが重要です。すべてを一度に改善する必要はありません。優先順位をつけて、段階的に改善していきましょう。
まず最初に取り組むべきこと
現在のサイトの現状分析から始めましょう。検索順位のチェック、スマホでの表示確認、情報の正確性確認など、問題点を明確にすることが改善の第一歩です。
次に、患者さんの視点でサイトを見直してみてください。実際に患者さんになったつもりで、「この医院に通いたいと思うか」「不安は解消されるか」を厳しくチェックしましょう。
専門家への相談の重要性
技術的な改善や本格的なSEO対策は、専門的な知識が必要です。自院で対応できる範囲を超える問題については、歯科医院専門のホームページ制作会社に相談することをお勧めします。
重要なのは、単に「安い」制作会社ではなく、歯科医院の特性を理解し、医療広告ガイドラインにも精通した専門業者を選ぶことです。
継続的な改善の重要性
ホームページの改善は一度行えば終わりではありません。患者さんのニーズや競合の状況は常に変化しているため、継続的な改善が必要です。
月1回程度の頻度で、アクセス状況や問い合わせ件数をチェックし、効果的な部分はさらに強化し、効果の低い部分は改善を図るというサイクルを継続することで、着実に集患効果を向上させることができます。
まとめ
ホームページを作ったのに患者さんが来ない場合、必ず改善できる原因があります。検索対策の不備、患者目線の不足、信頼感の欠如、スマホ対応の問題、更新の怠りという5つの失敗パターンを理解し、段階的に改善していくことで、ホームページは確実に集患効果を発揮するようになります。重要なのは、現状を正しく把握し、患者さんの立場に立った改善を継続することです。
投稿者プロフィール
-
歯科コンサルタント小澤直樹
2002年よりコンサルティング活動を開始。2008年から歯科コンサルタントとして勤務した後20017年より現職。
最新の投稿
 トラブル・リスク管理2026年1月22日「医療広告ガイドライン違反」で指導を受けたらどうする?対応手順
トラブル・リスク管理2026年1月22日「医療広告ガイドライン違反」で指導を受けたらどうする?対応手順 予約・CRM・システム連携2026年1月21日LINEで予約・リマインド・問診!歯科医院のCRM活用術
予約・CRM・システム連携2026年1月21日LINEで予約・リマインド・問診!歯科医院のCRM活用術 SNS・外部連携2026年1月20日Facebook広告×LP(ランディングページ)で自費診療患者を獲得する方法
SNS・外部連携2026年1月20日Facebook広告×LP(ランディングページ)で自費診療患者を獲得する方法 UI・UX・デザイン2026年1月19日「見やすい」「分かりやすい」を実現する!情報設計(IA)の基本
UI・UX・デザイン2026年1月19日「見やすい」「分かりやすい」を実現する!情報設計(IA)の基本
ホームページ制作のご相談・資料請求はこちら
現在運用中のホームページのセカンドオピニオンや、開業時のご相談も柔軟にうけたまわります。先生がお手すきのときに、お電話でご連絡をいただくのも大歓迎です。

