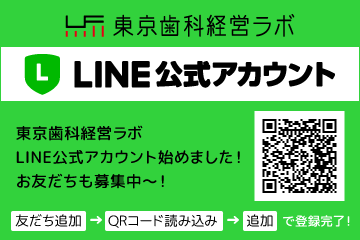患者数が減少している歯科医院が今すぐ取り組むべき5つの対策【2025年最新版】
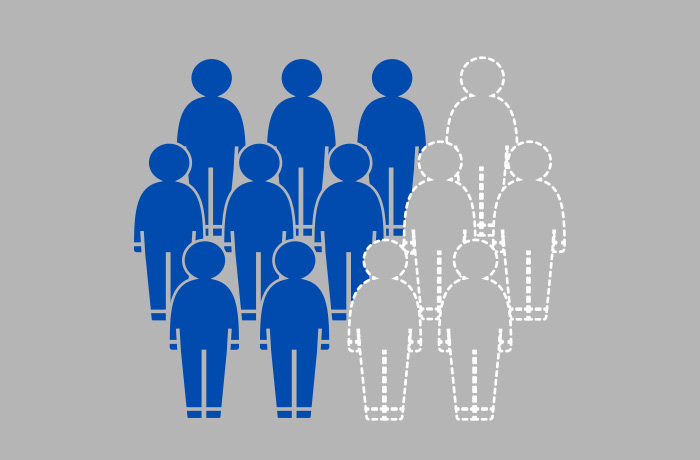
歯科医院の患者数減少は、多くの歯科医師が直面する深刻な経営課題です。厚生労働省の調査によると、全国の歯科診療所数は約68,000件を超え、コンビニエンスストアよりも多い状況となっています。この激しい競争環境の中で、患者数を維持・増加させるためには戦略的なアプローチが不可欠です。
本記事では、歯科医院コンサルティングの専門家として数百の歯科医院の経営改善を支援してきた経験をもとに、患者数減少に悩む歯科医院が今すぐ実践できる5つの具体的対策をご紹介します。これらの集患対策は、実際に患者数20%以上の増加を実現した歯科医院で検証済みの手法です。
1. 歯科医院の患者数が減少する主な原因とは?

対策を講じる前に、なぜ患者数が減少するのかを理解することが重要です。当社の調査分析では、競合歯科医院の増加による地域内の歯科医院密度の上昇が最も大きな要因となっています。また、患者の受診行動も大きく変化しており、予防意識の高まりによって従来の治療中心の受診パターンから定期検診重視へとシフトしています。
さらに、デジタルマーケティングへの対応の遅れも深刻な問題です。現代の患者の約80%が歯科医院選びにインターネットを活用しているにも関わらず、多くの歯科医院がオンライン集患への対応が不十分な状況にあります。加えて、患者満足度の低下やリコールシステムの機能不全も患者離脱の大きな要因となっています。
これらの複合的な原因を踏まえた上で、効果的な歯科医院集患対策を詳しく見ていきましょう。
2.既存患者のリコール率向上で安定した患者数を確保
なぜリコール率向上が最優先なのか
新患獲得コストは既存患者維持コストの5倍と言われています。歯科医院経営において、まず取り組むべきは既存患者の定期検診率(リコール率)の向上です。リコール率を10%向上させることで、月間患者数を15-20%増加させることが可能になります。
効果的なリコール率向上の具体的方法
現在のリコール率が70%以下の歯科医院は、まず80%を目標に設定することから始めましょう。最も効果的な手法は「予約時予約」の徹底です。メンテナンス終了時に次回予約を必ず取ることで、患者の継続来院率を大幅に改善できます。
リコール連絡においては、3段階システムの導入が重要です。予定日の2週間前に初回連絡を行い、1週間前に確認連絡、そして前日にリマインド連絡を実施することで、リコール率の向上と無断キャンセルの削減を同時に実現できます。
また、患者一人ひとりの口腔状態に応じた個別リコール間隔の設定も効果的です。一律3ヶ月ではなく、歯周病の進行度や口腔衛生状態に応じて2ヶ月から6ヶ月まで個別に設定することで、患者により適切なケアを提供できます。
リコール内容の付加価値向上も欠かせません。単なる歯石除去だけでなく、口腔内写真による現状説明と経時変化の可視化を行うことで、患者自身が口腔状態の改善を実感できるようになります。さらに、個別予防プログラムの提案や生活習慣に応じたホームケア指導を充実させることで、「行く価値のある」リコールに変えていくことができます。
3. 患者満足度を高める院内環境とサービス改善

患者が歯科医院を変える本当の理由
歯科医院のマーケティング調査では、患者が転院する理由の約65%が「治療技術」以外の要因であることが判明しています。つまり、患者体験(Patient Experience)の改善が集患の鍵となるのです。
多くの歯科医師は治療技術の向上に注力しがちですが、実際には電話応対の印象、待ち時間の長さ、スタッフの対応、院内の雰囲気といった要素が患者の満足度により大きな影響を与えています。
患者満足度向上の実践ポイント
患者目線での院内監査を定期的に実施することから始めましょう。初診患者の立場で電話予約から会計まで一連の流れを体験し、問題点を洗い出します。特に電話応対品質の向上は重要で、明るく丁寧な応対と適切な予約調整により、来院前の患者の不安を軽減できます。
待ち時間の最適化については、予約枠の見直しによる待ち時間短縮が最も効果的です。同時に、待合室環境の充実も重要で、WiFi環境の整備、最新雑誌の配置、子供向けスペースの確保により、待ち時間を有効活用できる環境を整えます。
診療室では、ビジュアルツールを活用した分かりやすい説明を心がけます。患者が理解しやすい言葉での説明と、レントゲンや口腔内写真を使った視覚的な説明により、治療への理解と納得を深めることができます。
痛みに配慮した治療環境づくりも患者満足度に直結します。無痛治療への取り組みとその詳細な説明、治療中の声かけとコミュニケーション、リラックスできる診療室環境の整備により、歯科治療への不安を大幅に軽減できます。
4. デジタルマーケティングを活用した新患獲得

歯科医院のオンライン集患戦略
現代の患者の約80%が歯科医院選びにインターネットを活用しており、デジタルマーケティングは歯科医院集患の必須要素となっています。特に重要なのは、地域での検索上位表示を実現するGoogleマイビジネスの最適化です。
Googleマイビジネスでは、正確で詳細な医院情報の登録から始まります。営業時間、電話番号、住所などの基本情報を正確に入力し、定期的に更新することが重要です。高品質な院内写真やスタッフ写真の掲載により、患者に安心感と親近感を与えることができます。
患者からの口コミへの対応も集患に大きく影響します。すべての口コミに対して丁寧で迅速な返信を行うことで、見込み患者に対して医院の誠実さと患者への配慮をアピールできます。また、定期的な投稿による情報発信を通じて、医院の活発さと専門性を示すことも効果的です。
ホームページ最適化による集患効果向上
ホームページのSEO対策では、「地域名 + 歯科」「地域名 + 歯医者」での検索上位表示を目指します。スマートフォン対応とページ表示速度の最適化は基本中の基本で、これらが不十分だと検索順位に大きく影響します。
患者が最も知りたい情報である料金、治療期間、痛みの程度については、明確で分かりやすく記載することが重要です。曖昧な表現ではなく、具体的な数値や期間を示すことで、患者の不安を軽減し、来院への動機を高めることができます。
医院の特徴や強みの明確な訴求も欠かせません。他院との差別化ポイントを具体的に示し、なぜこの医院を選ぶべきかを患者に分かりやすく伝える必要があります。患者の声や症例写真の掲載(適切な同意取得済み)により、実際の治療効果と患者満足度を視覚的に示すことも効果的です。
5. 地域密着型マーケティングで信頼関係を構築
アナログマーケティングの重要性
デジタル全盛の時代でも、歯科医院は地域密着型ビジネスの性格を強く持っています。地域コミュニティとの関係構築は、長期的な集患効果を生み出す重要な要素です。
地域貢献活動への積極的な参加により、医院の認知度向上と信頼関係の構築を図ることができます。地域のお祭りや健康イベントへの参加、学校での歯科健診ボランティア、高齢者施設での口腔ケア講座開催などを通じて、地域住民との接点を増やします。
医療機関連携による相互紹介システム
近隣の内科や小児科との患者紹介システムの構築は、安定した新患獲得につながります。特に、糖尿病患者の歯周病治療や小児の予防歯科において、医科との連携は患者にとって大きなメリットとなります。
薬局との連携による相互紹介も効果的です。薬剤師は地域住民との接点が多く、口腔ケアに関する相談を受ける機会も少なくありません。薬局スタッフとの良好な関係を築くことで、自然な形での患者紹介を実現できます。
介護施設との訪問歯科連携や他の歯科医院との専門分野での連携により、医院の専門性を地域内でアピールすることも重要です。これらの連携関係は、単なる患者紹介に留まらず、医院の信頼性と専門性の向上にも寄与します。
6. 診療メニューの最適化と自費診療率向上

時代に合わせた診療メニューの見直し
患者ニーズの多様化に対応するため、従来の治療中心から予防・審美・機能性を重視したメニュー構成への転換が必要です。働く世代には短時間で効率的な治療と包括的な予防プログラムを提供し、高齢者には機能回復と維持に重点を置いた診療メニューを用意します。
子育て世代に対しては、家族全体でのケアプログラムや子供の予防教育に力を入れることで、長期的な患者関係を構築できます。審美意識の高い層に向けては、ホワイトニングやセラミック治療などの審美歯科メニューを充実させることが効果的です。
自費診療の適切な提案方法
自費診療率の向上は医院収益の安定化に直結しますが、患者の価値観に合わせた選択肢提供が重要です。保険治療と自費治療の違いを明確に説明し、長期的なメリットとデメリットを客観的に提示することで、患者自身が納得して選択できる環境を整えます。
分割払いシステムの導入により、患者の経済的負担を軽減し、より良い治療を受けやすくすることも効果的です。治療後の保証制度を充実させることで、患者の不安を軽減し、自費診療への移行を促進できます。
重要なのは、患者に無理に勧めるのではなく、十分な情報提供と時間をかけた検討機会を提供することです。患者が自ら選択したと感じられる提案プロセスを構築することで、長期的な信頼関係と安定した自費診療収入を実現できます。
7.スタッフ教育とチーム力強化で総合的な医院力向上
患者数増加は院長だけでは実現できません。受付スタッフから歯科衛生士まで、全スタッフが患者満足度向上に貢献する意識とスキルを持つことが重要です。
定期的な接遇研修の実施により、電話応対スキルの向上、患者対応力の強化、クレーム対応力の向上を図ります。特に重要なのは、患者の立場に立った対応ができるよう、ロールプレイング研修を継続的に実施することです。
患者情報共有システムの活用により、患者一人ひとりの情報を全スタッフで共有し、パーソナライズされたサービスを提供します。患者の治療履歴、個人的な特徴、家族構成などを把握することで、より温かみのある対応が可能になります。
チームワーク向上のための定期ミーティングでは、患者からの意見やクレームを全員で共有し、改善策を検討します。スタッフ全員が医院の方向性と目標を共有することで、統一感のあるサービス提供を実現できます。
8.まとめ:継続的な改善で確実な患者数増加を実現
歯科医院の患者数減少問題は、これらの5つの対策を継続的に実践することで必ず改善できます。まず既存患者のリコール率向上により即効性のある効果を実現し、同時に患者満足度改善による基盤づくりを進めます。その上で、デジタルマーケティング強化による中長期的な集患効果と、地域マーケティング展開による信頼関係構築を図ります。最終的に診療メニューの最適化により収益性の向上を実現するという段階的なアプローチが重要です。
これらの歯科医院集患対策により、3ヶ月以内に患者数10%以上の増加、6ヶ月以内に20%以上の増加を実現した事例が数多くあります。重要なのは、すべての対策を同時並行で進めながら、継続的な改善を行うことです。
当社では、個別の歯科医院の状況に合わせて、これらの対策を最適化し、具体的な実行支援を行っています。患者数減少にお悩みの歯科医院様は、まずは現状分析から始めてみませんか。一緒に持続可能な歯科医院経営を実現していきましょう。
無料相談/経営コンサルティングについてお問合せ
経営相談をしようかどうか迷われている先生。
ぜひ思い切ってご連絡ください。先生のお話を、じっくり先生のペースに合わせてうかがいます。まずはそこから。
先生が「今が経営改善のときかも」と感じたときが、動くべきタイミングです。ご連絡お待ちしています。