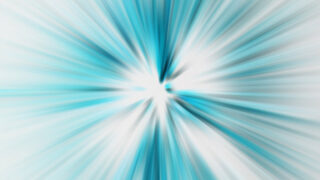歯科医院のオンライン診療システムとホームページ連携ガイド【2025年版】

新型コロナウイルスの影響をきっかけに、医療のオンライン化が急速に進みました。2025年現在、オンライン診療は内科や皮膚科だけでなく、歯科医院でも活用の幅が広がっています。
「歯科でオンライン診療なんて無理では?」と思われるかもしれません。確かに、歯を削ったり詰めたりする処置はオンラインではできません。しかし、初診前の相談、治療後のフォローアップ、矯正治療の経過観察、口腔ケア指導など、オンラインで対応できる場面は意外と多いのです。
本記事では、歯科医院におけるオンライン診療システムの導入方法と、ホームページとの効果的な連携方法を解説します。患者さんの利便性を高めながら、医院の収益向上にもつながる実践的なガイドです。
目次
1. 歯科医院でできるオンライン診療とは
2. オンライン診療システムの選び方
3. ホームページとの連携で実現できること
4. 導入のステップと必要な準備
5. 効果的な運用方法と収益化
6. 法規制と保険診療の注意点
7. 実践事例:オンライン診療を成功させた歯科医院★
8. まとめ
1.歯科医院でできるオンライン診療とは
歯科におけるオンライン診療の位置づけ
歯科医療の多くは対面での処置が必要です。しかし、すべての診療が対面である必要はありません。オンライン診療は、対面診療を補完し、患者さんとのコミュニケーションを円滑にするツールとして活用できます。
オンライン診療を導入することで、通院が難しい患者さんへのサポート、遠方からの相談対応、治療のハードルを下げる初回相談など、新しい患者接点を作ることができます。
オンライン診療が活用できる5つの場面
まず、初診前のカウンセリングです。「歯が痛いけど、どんな治療になるか不安」「インプラントに興味があるけど、まず話を聞きたい」といった患者さんに対し、オンラインで無料相談を提供できます。このハードルの低さが、来院のきっかけになります。
次に、治療後のフォローアップです。抜歯後の経過確認、インプラント手術後のチェック、詰め物をした後の違和感の確認など、わざわざ来院しなくても画面越しで状態を確認できる場合があります。
矯正治療の経過観察も、オンライン診療に適しています。マウスピース矯正では、定期的な装着状況の確認や歯の動きのチェックをオンラインで行い、問題がある時だけ来院してもらう方式が広がっています。
口腔ケア指導やブラッシング指導も効果的です。正しい歯磨き方法、フロスの使い方、お子様の仕上げ磨きの方法などを、画面を共有しながら丁寧に指導できます。患者さんは自宅で実際に歯ブラシを持ちながら学べるため、理解度が高まります。
セカンドオピニオンの提供も、オンライン診療の有効な活用法です。他院で治療方針を提示された患者さんが、セカンドオピニオンを求めてオンラインで相談。その結果、信頼を得て転院してくるケースもあります。
オンライン診療のメリット
患者さんにとってのメリットは、移動時間と待ち時間の削減です。仕事や育児で忙しい方、高齢で移動が困難な方、遠方に住んでいる方でも、気軽に相談できます。
医院にとってのメリットは、新患獲得の間口が広がることです。「いきなり来院はハードルが高い」という潜在患者さんを取り込めます。また、診療の効率化も図れます。簡単な経過確認はオンラインで済ませ、本当に必要な患者さんに診療時間を充てられます。
さらに、自費診療の相談がしやすくなる点も見逃せません。インプラントや矯正などの高額治療は、患者さんも慎重に検討します。オンラインでじっくり相談できる環境があれば、成約率が高まります。
2.オンライン診療システムの選び方
主要なオンライン診療システム
2025年現在、歯科医院で利用されている主なオンライン診療システムには、CLINICS、curon、YaDoc、LINEドクターなどがあります。それぞれ特徴が異なるため、自院のニーズに合ったシステムを選ぶことが重要です。
CLINICSは、医療機関向けのオンライン診療システムとして実績が豊富で、予約から決済までをワンストップで提供します。curonはシンプルで使いやすく、初めてオンライン診療を導入する医院に適しています。
YaDocは、保険診療にも対応しており、診療報酬の請求までサポートしてくれます。LINEドクターは、患者さんが普段使っているLINEアプリから利用できるため、新たなアプリのインストールが不要で、患者さんの心理的ハードルが低いのが特徴です。
選定時の5つのチェックポイント
まず、使いやすさです。院長先生やスタッフが簡単に操作できるか、患者さんにとっても分かりやすいかを確認しましょう。複雑なシステムは、導入しても使われなくなるリスクがあります。
次に、予約・決済機能です。オンライン診療の予約、クレジットカード決済、領収書発行などが一元管理できるシステムが便利です。別々のシステムを組み合わせると、運用が煩雑になります。
ホームページとの連携性も重要です。ホームページから直接オンライン診療の予約ができるか、埋め込み型の予約フォームが提供されているかを確認してください。スムーズな導線が、利用率を高めます。
セキュリティ対策も欠かせません。医療情報を扱うため、通信の暗号化、個人情報の保護、ガイドラインへの準拠が必須です。信頼できるシステムを選びましょう。
コストと契約形態も確認が必要です。初期費用、月額費用、診療ごとの手数料など、費用体系を理解しておきましょう。無料トライアル期間があるシステムなら、実際に試してから判断できます。
無料・低コストで始める選択肢
本格的なシステムを導入する前に、まずはZoomやGoogle Meetなどの一般的なビデオ通話ツールで試してみる方法もあります。医療専用ではありませんが、初回相談やフォローアップ程度なら十分に機能します。
ただし、予約管理や決済は別途対応が必要になります。また、医療情報のやり取りには慎重を期す必要があります。あくまで「試験的に始める」段階での選択肢と考えましょう。
3.ホームページとの連携で実現できること

オンライン診療予約ページの設置
ホームページに「オンライン診療のご案内」という専用ページを作ります。このページには、対応できる診療内容、料金、予約方法、利用の流れ、よくある質問を掲載します。
予約ボタンは目立つ位置に配置し、クリックするとオンライン診療システムの予約画面に遷移する仕組みを作ります。すべてのページのヘッダーやフッターに「オンライン診療予約」ボタンを設置すれば、どこからでもアクセスできます。
利用の流れを視覚的に説明
患者さんは「オンライン診療って、どうやって使うの?」という疑問を持ちます。ホームページで、利用の流れを図解やイラストで分かりやすく説明しましょう。
たとえば、「1. ホームページから予約」「2. 事前問診票の入力」「3. 予約時間にビデオ通話で診療」「4. クレジットカードで決済」「5. 必要に応じて処方箋を郵送」というステップを、番号付きの図で示します。
動画で説明するのも効果的です。実際にスマートフォンでオンライン診療を受ける様子を撮影し、2〜3分の説明動画を作成してホームページに埋め込みます。文字だけより圧倒的に分かりやすくなります。
初診前カウンセリングの導線設計
「いきなり来院するのはハードルが高いけど、まず相談したい」という潜在患者さんを取り込むため、無料のオンライン初診相談を設けます。ホームページのトップページに「初めての方限定 無料オンライン相談」というバナーを設置します。
このバナーをクリックすると、オンライン相談の説明ページに遷移し、「インプラントについて相談したい」「子どもの矯正について聞きたい」「歯の痛みについて相談したい」など、相談内容を選択できる予約フォームが表示されます。
無料相談を受けた患者さんの多くは、実際の来院につながります。オンラインで院長先生の人柄や医院の雰囲気を感じ、信頼関係が生まれるからです。
治療メニュー別のオンライン対応表示
診療案内ページの各治療メニューに、オンライン対応の可否を表示します。たとえば、インプラントのページには「オンライン無料相談可」、矯正歯科のページには「オンライン経過観察対応」、一般歯科のページには「治療後のオンラインフォローアップ可」といった情報を記載します。
これにより、患者さんは自分のニーズに合った利用方法を理解でき、オンライン診療のハードルが下がります。
患者さんの声でオンライン診療の良さを伝える
実際にオンライン診療を利用した患者さんの声をホームページに掲載します。「仕事が忙しくて通院が難しかったが、オンラインで相談できて助かった」「子どもを連れて歯科医院に行くのは大変だが、オンラインなら自宅で気軽に相談できる」といった具体的な声が、新たな患者さんの背中を押します。
4.導入のステップと必要な準備

ステップ1:目的とターゲットの明確化
まず、何のためにオンライン診療を導入するのか、目的を明確にします。新患獲得なのか、既存患者のサービス向上なのか、自費診療の相談対応なのか。目的が明確でないと、中途半端な導入になってしまいます。
次に、どんな患者さんをターゲットにするかを決めます。忙しいビジネスパーソン、小さな子どものいる親御さん、高齢で移動が困難な方、遠方に住んでいる方。ターゲットによって、提供すべきサービス内容が変わります。
ステップ2:システムの選定とテスト運用
複数のオンライン診療システムを比較検討し、自院に最適なものを選びます。可能であれば無料トライアル期間を利用し、実際に操作してみることをおすすめします。
選定後、まずはスタッフ間でテスト運用を行います。院長先生と受付スタッフ、歯科衛生士同士でビデオ通話を試し、音声や画質、操作性を確認します。問題があれば、本格導入前に解決しておきましょう。
ステップ3:運用ルールとマニュアルの整備
オンライン診療の対象となる診療内容、料金設定、予約の受付方法、キャンセルポリシー、緊急時の対応など、運用ルールを明文化します。
スタッフ向けには、オンライン診療の準備、患者さんへの案内方法、トラブル時の対処法などをまとめたマニュアルを作成します。これにより、誰でも一定水準のサービスを提供できるようになります。
ステップ4:ホームページへの情報掲載
オンライン診療の専用ページを作成し、ホームページに公開します。対応内容、料金、予約方法、利用の流れ、よくある質問を分かりやすく掲載しましょう。
トップページや診療案内ページに「オンライン診療対応」のバナーを設置し、患者さんの目に留まりやすくします。予約ボタンも複数箇所に配置して、導線を明確にします。
ステップ5:既存患者への周知
院内掲示やリーフレット、診察券に挟み込むチラシなどで、既存患者さんにオンライン診療を開始したことを知らせます。「治療後の経過確認がオンラインで可能になりました」「矯正治療の経過観察がご自宅から受けられます」など、具体的なメリットを伝えましょう。
また、SNSやメールマガジンでも告知します。特にInstagramやLINEは視覚的に訴求しやすく、若い世代に効果的です。
ステップ6:少数の患者さんでスタート
いきなり大々的に展開するのではなく、まずは数名の患者さんに試験的に利用してもらいます。フィードバックをもらい、改善点を洗い出します。
スタッフも慣れていないため、最初は戸惑うこともあるでしょう。少数から始めることで、トラブルを最小限に抑えながら、徐々にノウハウを蓄積できます。
5.効果的な運用方法と収益化

無料相談と有料診療の使い分け
初診前の相談は無料にすることで、ハードルを下げます。「まず話を聞いてみたい」という患者さんを取り込み、来院や有料オンライン診療につなげます。
一方、治療後のフォローアップや矯正の経過観察、詳しい口腔ケア指導などは有料サービスとして提供します。料金設定は、3,000円〜5,000円程度が一般的です。保険診療に比べて手間がかからないため、短時間で効率的に収益を得られます。
パッケージ化でリピートを促す
単発のオンライン診療だけでなく、パッケージ化することでリピートを促進できます。たとえば「矯正経過観察パック:月1回のオンライン診療×6ヶ月で2万円」「口腔ケアサポートプラン:月2回の歯磨き指導×3ヶ月で1.5万円」といった形です。
パッケージにすることで、患者さんは継続的にサポートを受けられ、医院は安定的な収益を得られます。
時間枠の設定と効率化
オンライン診療は、1件あたり15分〜30分程度に設定します。あまり長くすると非効率ですし、短すぎると十分な対応ができません。
診療の合間や休憩時間、診療終了後など、空いている時間枠にオンライン診療を入れることで、時間を有効活用できます。「毎週火曜日の13時〜14時はオンライン診療の時間」と固定するのも、運用しやすい方法です。
スタッフの役割分担
オンライン診療のすべてを院長が担う必要はありません。初回相談や簡単なフォローアップは歯科衛生士が対応し、専門的な判断が必要な場合のみ院長が対応する方式も効果的です。
受付スタッフは、予約管理、事前の問診票確認、決済処理などを担当します。役割分担を明確にすることで、スムーズな運用が実現します。
効果測定と改善
オンライン診療の利用状況を定期的に確認します。月に何件の予約があったか、どんな内容の相談が多いか、実際の来院につながった割合はどれくらいか。データを分析することで、改善点が見えてきます。
患者さんからのフィードバックも重要です。「使いやすかったか」「改善してほしい点はあるか」をアンケートで聞き、サービスの質を高めていきましょう。
6.法規制と保険診療の注意点
オンライン診療の指針と厚生労働省の方針
オンライン診療は、厚生労働省の「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に従って実施する必要があります。2025年現在、指針は継続的に見直されており、最新の情報を常に確認することが重要です。
基本的なルールとして、初診は原則として対面診療が必要ですが、一部の条件下では初診からのオンライン診療も認められています。歯科の場合、初診前の相談は診療ではなくカウンセリングとして位置づけられるため、比較的自由に実施できます。
保険診療でのオンライン診療
2025年現在、歯科でも一部の条件下で保険診療としてのオンライン診療が認められています。ただし、算定要件が細かく定められているため、事前に十分な確認が必要です。
保険診療でオンライン診療を行う場合、初診料や再診料に加えて、情報通信機器を用いた診療料を算定できます。ただし、施設基準の届出や診療計画書の作成など、必要な手続きがあります。
自費診療としての展開
保険診療の要件を満たすのが難しい場合、自費診療として展開する方法もあります。特に、インプラントや矯正などの自費診療メインの医院では、相談やフォローアップを自費のオンライン診療として提供する方が運用しやすいでしょう。
料金設定は自由ですが、患者さんが納得できる価格と内容のバランスが重要です。高すぎると利用されず、安すぎると労力に見合いません。相場は3,000円〜10,000円程度です。
個人情報保護とセキュリティ
オンライン診療では、映像や音声、診療情報などの個人情報を扱います。通信の暗号化、データの保管方法、第三者への開示防止など、個人情報保護法に則った対応が必須です。
使用するシステムが、医療情報のセキュリティ基準を満たしているか、事前に確認しましょう。また、患者さんに対して、どのように個人情報を扱うかを説明し、同意を得ることも重要です。
7.実践事例:オンライン診療を成功させた歯科医院

事例①:矯正歯科N医院のマウスピース矯正フォローアップ
矯正専門のN医院では、マウスピース矯正の患者さんに対してオンライン診療を導入しました。従来は月に一度来院してもらい経過を確認していましたが、オンラインでの確認に切り替えました。
患者さんは自宅でスマートフォンのカメラを使って口腔内を撮影し、歯の動きを確認します。問題がなければそのまま治療を続け、調整が必要な場合のみ来院してもらいます。
この仕組みをホームページで詳しく説明したところ、「通院回数が少なくて済む矯正治療」として注目され、遠方からの問い合わせが急増。月に10件だった矯正の新規相談が、30件に増加しました。
オンライン経過観察は1回3,000円の自費診療として提供し、患者さんの利便性を高めながら、医院の収益にも貢献しています。
事例②:一般歯科O医院の初診前無料相談
地方都市の一般歯科O医院では、新患獲得に課題を感じていました。そこで、ホームページに「初診前無料オンライン相談」のページを作成。「歯が痛いけど、どんな治療になるか不安」「費用が心配」といった患者さんの不安に、オンラインで答える仕組みを作りました。
トップページに大きく「まずは無料で相談」というバナーを設置し、クリックするとオンライン相談の予約ページに遷移します。相談は院長が15分程度対応し、必要に応じて来院を促します。
導入から3ヶ月で、月に20件の無料相談があり、そのうち15件が実際の来院につながりました。来院率75%という高い成果です。「いきなり歯医者に行くのはハードルが高いけど、まず相談できるなら」という潜在患者層を取り込むことに成功しました。
事例③:インプラント専門P医院のセカンドオピニオン
インプラント専門のP医院は、遠方からの患者さんも多く受け入れています。そこで、他院でインプラント治療を提案された患者さん向けに、有料のオンラインセカンドオピニオンサービスを開始しました。
料金は30分で1万円。他院の診断書やレントゲン写真をメールで事前に送ってもらい、オンラインで詳しく説明します。「本当にインプラントが必要なのか」「他の選択肢はないのか」「提示された費用は適正か」といった疑問に、専門医として答えます。
ホームページに「インプラントセカンドオピニオン」の専用ページを作り、サービス内容と料金を明記したところ、月に5〜8件の申し込みがありました。そのうち半数以上が、最終的にP医院でインプラント治療を受けることを選択。高額治療の成約につながっています。
8.まとめ
オンライン診療は、歯科医院にとって新しい患者接点を作り、サービスの幅を広げる有効なツールです。2025年現在、技術の進歩と法整備により、歯科医院でも実用的に活用できる環境が整っています。
歯科でオンライン診療が活用できる場面は、初診前カウンセリング、治療後のフォローアップ、矯正治療の経過観察、口腔ケア指導、セカンドオピニオンの提供など多岐にわたります。対面診療を完全に置き換えるのではなく、補完するものとして位置づけることが成功の鍵です。
システムを選ぶ際は、使いやすさ、予約・決済機能、ホームページとの連携性、セキュリティ対策、コストの5つのポイントを確認しましょう。無料トライアルを活用し、実際に試してから判断することをおすすめします。
ホームページとの連携では、オンライン診療予約ページの設置、利用の流れの視覚化、初診前カウンセリングの導線設計、治療メニュー別のオンライン対応表示、患者さんの声の掲載が効果的です。患者さんが「使ってみたい」と思える分かりやすい情報提供が重要です。
導入は段階的に進めましょう。目的とターゲットの明確化、システムの選定とテスト、運用ルールの整備、ホームページへの掲載、既存患者への周知、少数でのスタート。焦らず、一歩ずつ進めることで、スムーズな導入が実現します。
運用では、無料相談と有料診療の使い分け、パッケージ化によるリピート促進、時間枠の効率的な設定、スタッフの役割分担、効果測定と改善が成功のポイントです。継続的に改善を重ねることで、患者さんにも医院にもメリットのあるサービスに育てられます。
法規制や保険診療のルールは変更される可能性があるため、常に最新情報を確認してください。不明点があれば、厚生労働省の資料を確認するか、専門家に相談しましょう。
オンライン診療は、これからの歯科医療に欠かせないツールになっていくでしょう。早めに導入し、ノウハウを蓄積することで、競合医院との差別化にもつながります。
株式会社リバティーフェローシップでは、歯科医院のオンライン診療導入を、ホームページ制作と連携してトータルサポートしています。システムの選定、ホームページへの組み込み、運用ルールの整備、スタッフ研修まで、一貫してお手伝いいたします。
「オンライン診療を始めたいが、何から手をつければいいか分からない」「ホームページとうまく連携させたい」というご相談も大歓迎です。2025年の歯科医療の新しい形を、一緒に作っていきましょう。
投稿者プロフィール
-
歯科コンサルタント小澤直樹
2002年よりコンサルティング活動を開始。2008年から歯科コンサルタントとして勤務した後20017年より現職。
最新の投稿
ホームページ制作のご相談・資料請求はこちら
現在運用中のホームページのセカンドオピニオンや、開業時のご相談も柔軟にうけたまわります。先生がお手すきのときに、お電話でご連絡をいただくのも大歓迎です。