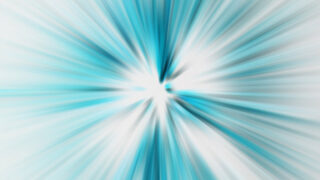クレーム予防に効果絶大!「セカンドオピニオンについて」等の事前説明ツール活用術
目次
1. 歯科医院のクレームが増加している背景
2. 事前説明ツールがクレームを70%削減する理由
3. 必須の5つの事前説明ツールと活用法
4. ホームページで患者様の期待値を適正化する方法
5. トラブル予防に効く院内掲示・配布物の作り方
6. まとめ
1.歯科医院のクレームが増加している背景

近年、歯科医院へのクレームや苦情が増加傾向にあります。国民生活センターへの歯科治療に関する相談件数は、年間約1000件を超え、その多くが「説明不足」「期待していた結果と違う」「費用が高すぎる」といった内容です。
クレームが増えている最大の理由は、インターネットの普及により患者様の情報収集力が高まったことです。治療前にネットで調べた情報と、実際の治療内容や費用が異なると感じた際に、不満が生まれやすくなっています。また、SNSの普及により、不満を簡単に発信できる環境も、クレームの増加に拍車をかけています。
さらに、患者様の権利意識の高まりも要因の一つです。医療は一方的に受けるものではなく、十分な説明を受けた上で自分で選択する権利があるという認識が浸透しています。この意識変化に、医院側の対応が追いついていないケースが多いのです。
クレームは医院の評判を傷つけるだけでなく、スタッフの精神的負担や業務効率の低下をもたらします。ある調査では、1件の深刻なクレーム対応に平均10時間以上が費やされ、その間の機会損失は数十万円に及ぶとされています。クレーム予防は、もはや歯科医院経営における最重要課題の一つなのです。
2.事前説明ツールがクレームを70%削減する理由

事前説明ツールとは、治療前に患者様へ提供する書面やデジタルコンテンツで、治療内容、リスク、費用、選択肢などを分かりやすく説明するものです。このツールを活用することで、クレームを大幅に削減できます。
第一の効果は、認識のズレを防げることです。口頭での説明だけでは、患者様が聞き逃したり誤解したりする可能性がありますが、書面やデジタルツールで提供すれば、患者様は自宅でも繰り返し確認できます。「聞いていない」「そんな説明は受けていない」というトラブルを防げます。
第二の効果は、患者様の期待値を適正化できることです。たとえば「セカンドオピニオンは患者様の権利です」と事前に伝えることで、医院に対する不信感を抱かせずに、他院での相談を受け入れる姿勢を示せます。透明性が信頼を生み、結果的にクレームが減少します。
第三の効果は、医院のリスク管理になることです。事前に十分な説明を行い、患者様の同意を得ていることを記録として残せば、万が一トラブルになった際の証拠となります。法的な紛争に発展するリスクも大幅に低減できます。
実際に事前説明ツールを導入した医院では、患者様からのクレームが約70%減少したというデータがあります。説明の質と透明性の向上が、患者満足度を高め、トラブルを未然に防いでいるのです。
3.必須の5つの事前説明ツールと活用法
クレーム予防に効果的な事前説明ツールを5つご紹介します。これらを適切に活用することで、患者様とのコミュニケーションが円滑になり、トラブルを防げます。
ツール1:セカンドオピニオンについての説明文書
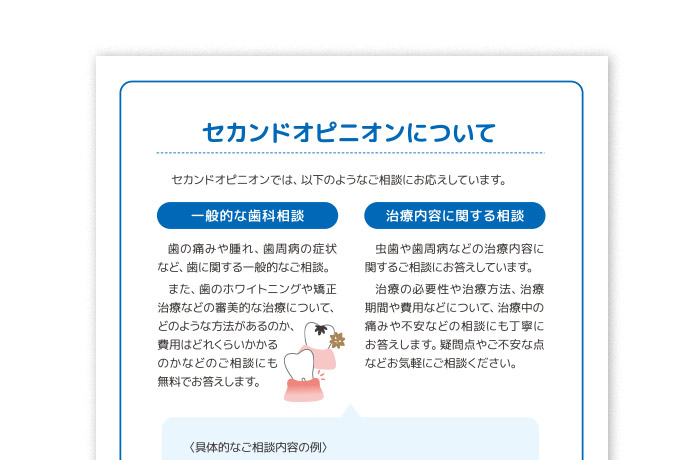
「セカンドオピニオンは患者様の大切な権利です」という姿勢を明示した文書を作成します。内容には、セカンドオピニオンとは何か、いつ利用すべきか、当院での対応方法(診断書・レントゲン提供など)を記載します。
このツールをホームページに掲載し、初診時にも配布することで、「他の医院でも相談したい」と言い出しやすい雰囲気を作ります。患者様が遠慮なく選択できる環境が、最終的に医院への信頼につながります。
〈lftool〉※DLできるようにリンク設置
・lftool_セカンドオピニオンについて.pdf
ツール2:自費診療の説明・同意書
自費診療に関しては、治療内容、期間、費用総額、リスク・副作用、保証内容を明記した説明書と同意書を用意します。特に重要なのは、保険診療との違いを比較表で示すことです。
同意書には患者様の署名をいただき、カルテとともに保管します。これにより「そんなに高いと思わなかった」「リスクを聞いていない」といったクレームを防げます。
〈lftool〉※DLできるようにリンク設置
・lftool_自費補綴物保証内容.pdf
・lftool_自由診療保証書2025<患者様署名あり>.docx
ツール3:治療計画書と費用見積書
治療開始前に、全体の治療計画と費用見積を書面で提示します。治療のゴール、各ステップの内容、所要期間、各ステップの費用を明記し、患者様が全体像を理解できるようにします。
途中で計画変更が必要になった場合は、必ず患者様に説明し、同意を得た上で新しい計画書を発行します。一方的な変更はクレームの温床となるため、常に患者様の理解と同意を確認します。
ツール4:治療のリスクとデメリット説明資料
どんな治療にもリスクやデメリットがあります。インプラントなら術後の腫れや感染リスク、矯正治療なら痛みや食事制限など、起こりうる不都合を事前に説明する資料を用意します。
「こういうことが起こる可能性があります」と事前に伝えておけば、実際に起きた際も「説明されていたこと」として受け入れられやすくなります。隠さず正直に伝える姿勢が、信頼関係を強化します。
ツール5:キャンセル・変更ポリシーの明示
予約のキャンセルや変更に関するルールを、ホームページと院内掲示で明示します。「前日までのキャンセルは無料、当日キャンセルはご相談ください」など、柔軟性を持たせつつも基本ルールを示します。
ただし、威圧的な表現は避け、「他の患者様のためにも、できるだけ早めのご連絡をお願いします」という協力依頼の形式が効果的です。
〈lftool〉※DLできるようにリンク設置
・lftool_POP_予約キャンセルについて.pdf
4.ホームページで患者様の期待値を適正化する方法

来院前にホームページで適切な情報提供を行うことで、患者様の期待値を適正化し、クレームを未然に防げます。
診療方針を明確に示す
トップページや医院紹介ページで、「当院が大切にしていること」を明確に示します。たとえば「丁寧な説明を心がけています」「患者様の選択を尊重します」「セカンドオピニオンを歓迎します」といったメッセージです。
事前に医院の姿勢を理解した上で来院する患者様は、医院の方針を受け入れやすく、トラブルになりにくい傾向があります。
治療の流れと所要時間を詳細に
初診から治療完了までの流れを、ステップごとに説明します。「初診は60分程度かかります」「精密検査には別途5000円必要です」など、具体的な情報を提供することで、「こんなに時間がかかるとは」「追加費用を請求された」といった不満を防げます。
よくある質問(FAQ)を充実させる
患者様が抱きやすい疑問を先回りして答えるFAQページを設置します。「治療費はどれくらいかかりますか?」「痛みはありますか?」「保険は使えますか?」など、30項目程度を用意します。
疑問が解消された状態で来院する患者様は、不安が少なく、スムーズなコミュニケーションが可能になります。
治療のリスクも正直に記載
良いことばかりでなく、治療のリスクや限界も正直に記載します。「インプラントは誰でもできるわけではありません」「矯正治療には2年から3年かかります」といった現実的な情報を提供することで、過度な期待を防げます。
透明性の高い情報発信が、結果的に信頼できる医院というブランディングにつながります。
5.トラブル予防に効く院内掲示・配布物の作り方

ホームページだけでなく、院内でも視覚的なツールを活用することで、クレーム予防効果が高まります。
待合室のポスター・掲示物
待合室には、以下のような内容のポスターを掲示します。
- 「治療について分からないことがあれば、遠慮なくお聞きください」
- 「セカンドオピニオンは患者様の権利です。ご希望の方はお申し付けください」
- 「当院の診療方針」(丁寧な説明、患者様の選択を尊重、など)
これらの掲示物により、患者様は「質問しても大丈夫」「他院で相談しても良い」と安心し、不満を溜め込まずに済みます。
会計時の配布資料
治療終了後、会計時に「本日の治療内容」と「次回の予定」を記載した資料を手渡します。簡潔でも構わないので、「今日何をしたか」「次は何をするか」が分かる情報があると、患者様の理解度が高まります。
特に高齢の患者様は、口頭での説明を忘れてしまうことがあるため、書面での確認が重要です。
受付カウンターの案内カード
受付には、「困ったことがあればお気軽にご相談ください」という案内カードを設置します。裏面には、よくある質問への回答や、相談窓口(受付、歯科衛生士、院長など)を記載します。
小さなカードでも、患者様が手に取りやすく、持ち帰って家族と相談することもできます。
デジタルサイネージの活用
待合室にデジタルサイネージ(電子掲示板)を設置し、治療の流れ、費用の目安、よくある質問などをスライドショー形式で表示します。待ち時間に自然と目に入るため、情報の刷り込み効果があります。
また、季節ごとに「年末年始の診療案内」「医療費控除のお知らせ」など、タイムリーな情報を表示することで、患者様とのコミュニケーションツールとしても機能します。
まとめ
歯科医院へのクレームは、患者様の情報収集力と権利意識の高まりにより増加傾向にあります。しかし、適切な事前説明ツールを活用することで、クレームを70%削減することが可能です。
特に重要なのは、セカンドオピニオンについての説明、自費診療の同意書、治療計画書、リスク説明資料、キャンセルポリシーという5つのツールです。これらを治療前に提供することで、患者様の理解と同意を確実に得られ、「聞いていない」「説明不足」というトラブルを防げます。
ホームページでは、診療方針の明示、治療の流れの詳細説明、充実したFAQ、リスクの正直な記載により、来院前から患者様の期待値を適正化できます。透明性の高い情報発信が、信頼できる医院としてのブランディングにつながります。
院内でも、待合室のポスター、会計時の配布資料、案内カード、デジタルサイネージなどを活用し、視覚的に情報を伝え続けることが重要です。患者様が「質問しやすい」「選択の自由がある」と感じられる環境づくりが、クレーム予防の基本です。
クレーム対応には膨大な時間とコストがかかりますが、事前説明ツールの整備は一度行えば長期的に効果を発揮します。今日から5つのツールを整備し、透明性の高いコミュニケーションを実践してください。患者様との信頼関係が深まり、安心して通える医院として選ばれ続けることができます。
無料ツールを今すぐダウンロード!
今回ご紹介した内容以外にも、様々な医院経営の取り組みに役立つ便利なツールを無料でご提供しています!歯科医院の集患や経営改善に役立つ実用的なツールをぜひお試しください。
※ツールご利用時のご注意※
弊社作成ツールは、院内利用に限り無償活用いただけます。
インターネット上へのアップは、弊社にてHPを制作した医院に限らせていただきます。たとえ多少の加工を加えたとしても、SNSやHPでの掲載はお控えいただきますようお願い申し上げます。
ラボストアはこちら
https://tdmlab-store.com/
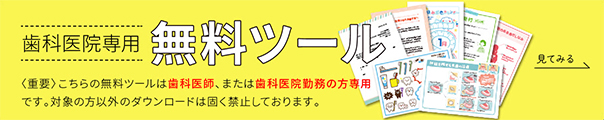
さらに、弊社のホームページ制作サービスをお申込みいただいた方には、上記ラボストアには未公開の特別なツールもご案内可能です。ホームページ制作とあわせて、医院経営のさらなる効率化にお役立てください!
投稿者プロフィール
-
歯科コンサルタント小澤直樹
2002年よりコンサルティング活動を開始。2008年から歯科コンサルタントとして勤務した後20017年より現職。
最新の投稿
ホームページ制作のご相談・資料請求はこちら
現在運用中のホームページのセカンドオピニオンや、開業時のご相談も柔軟にうけたまわります。先生がお手すきのときに、お電話でご連絡をいただくのも大歓迎です。